皆さん、こんにちは。
炭酸飲料はカロリーゼロ派、あい駒形クリニックの高橋秀行です。
本シリーズでは、これまで何度かご紹介している当院の「耳鼻科往診」について、詳しくご説明してゆきたいと思います。
今日は、のどの診察についてお話したいと思います。

「のど」と言っても幅広い
「のど」と書きましたが、耳鼻科でのどを診る場合、口腔・上咽頭・中咽頭・下咽頭・喉頭の5部位を主な対象とします。
このため、自覚症状や所見も非常に多彩であり、問診による部位や疾患の絞り込みがとても大切になります。
口腔
口腔(口の中)の症状ですと、舌の痛みやピリピリ感、口内炎、そして味覚障害が代表的です。
舌の痛みやピリピリ感は舌の炎症のことが多いですが、腫瘍の可能性は常に頭の片隅に置きながら、視診で所見を確認します。
味覚障害は新型コロナウイルス感染症でクローズアップされましたが、感冒後や亜鉛の不足で生じる味覚障害は患者さんも少なくありません。
治療として、亜鉛欠乏が原因の場合は亜鉛製剤の内服を行います。
コロナ後遺症の味覚障害については、残念ながらまだ確立された治療方法がないのが現状です。
咽頭
咽頭は上・中・下の3部位に分けられ、鼻の突き当りから食道との境界までの比較的広い範囲を指します。
咽頭に関連する症状としては、のどの痛みや違和感、飲み込みにくい等の症状が代表的です。
中でも頻度の多い症状である痛みの場合、中咽頭から下咽頭にかけての炎症であることが多く、ウイルスや細菌、時に真菌(カビ)の感染が原因として挙げられます。
寝ている間に胃酸が逆流し咽頭に炎症を起こすこともあります。
また、鼻の奥からのどにかけての痛みの場合、炎症が上咽頭まで拡がっていることもあります。
一方、「のどの違和感」「のどがつっかえる感じ」「のどが張り付く感じ」といった症状を訴える方も多いですが、こういった症状の場合は明らかな異常所見を認めないことがほとんどです。
このため原因がはっきりしないことが多いのですが、精神的な要因や加齢性変化、脱水等が背景にあることが多く、問診によりこういった背景を解き明かすことが大切になります。
稀ですが腫瘍性病変のこともありますので、このような症状が続く場合は内科だけでなく耳鼻咽喉科への受診もご検討ください。
喉頭
最後に喉頭ですが、喉頭はいわゆる「のどぼとけ」を指します。
喉頭は軟骨で囲まれたスペースで、声を出す声帯と言われる部位があります。
声帯に異常が起きると、声が枯れたり、呼吸が苦しくなる、等の症状が現れます。
咽頭と同じく感染による炎症の頻度が多いですが、中には声帯ポリープや喉頭がん等の疾患が隠れていることもあり、1ヶ月以上続く声枯れの場合は耳鼻科への受診が必要となります。

のどの診察に役立つ内視鏡
「のど」の診察の場合、口から直接観察出来る部位は限られているため、上咽頭や下咽頭、喉頭を詳細に観察するためには内視鏡が役に経ちます。
通常は鼻の穴から挿入し、口からでは観察出来ない部位を詳細に観察することが出来ます。
当院は往診で使用可能な内視鏡を準備していますので、のどの症状のお困りの方は是非一度ご相談頂ければ幸いです。

耳鼻咽喉科は聴覚、嗅覚、味覚、発声といった、人間が生きてゆくうえで重要な感覚や機能を多く扱う診療科です。
どれもQOL(Quality Of Life)に直結する重要な部分だけに、耳鼻咽喉科医の果たす役割も大きいといえます。今後、耳鼻科往診を通じてのどの悩みをお持ちの患者様のお手伝いが出来るよう、精進してゆきたいと思います。
耳鼻科往診の解説シリーズ、今後も続けてゆきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました!



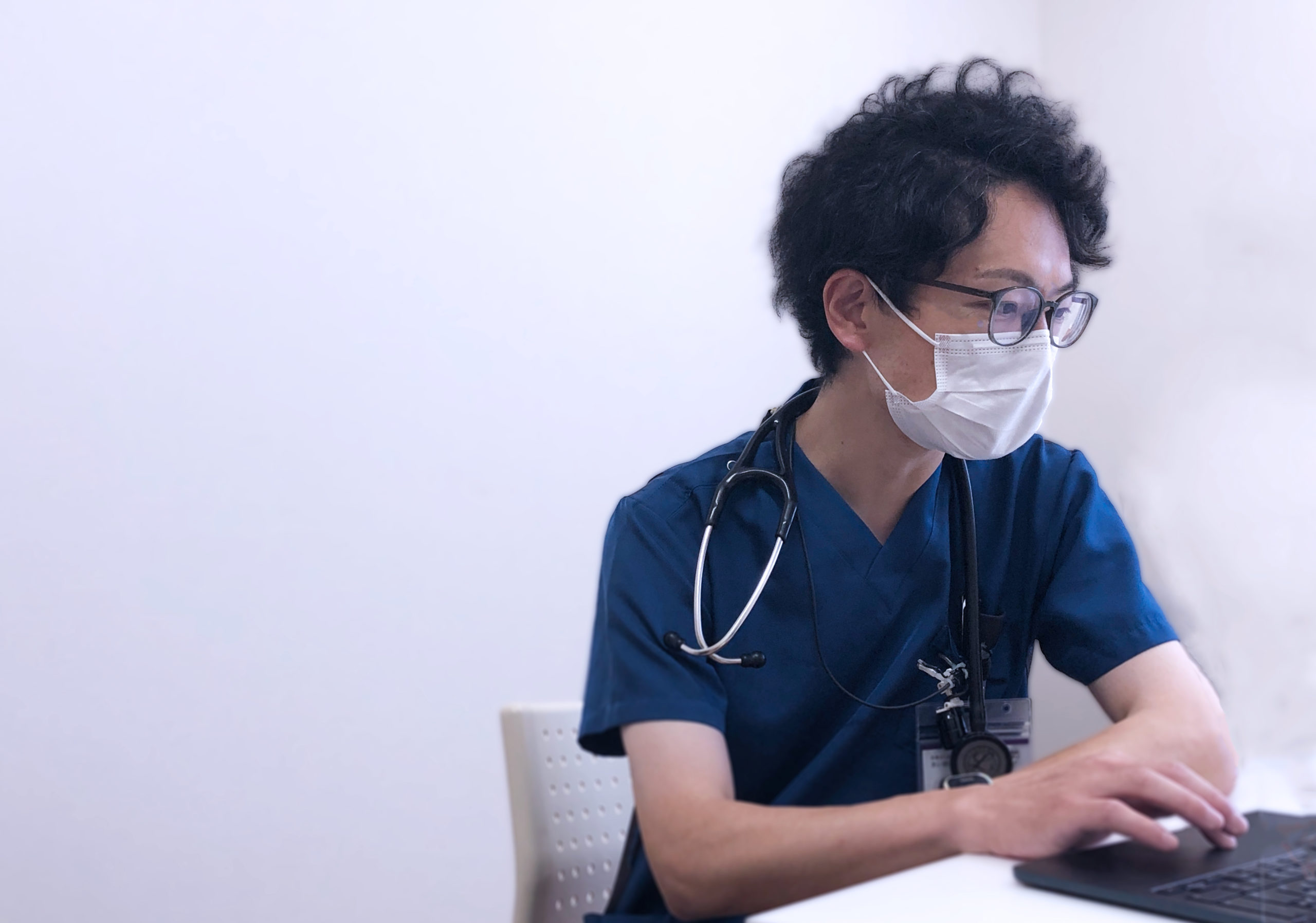




 FAX:027-226-1892
FAX:027-226-1892 



 FAX:027-226-1892
FAX:027-226-1892